2018.12.18
EU-JAPAN
文学で旅するヨーロッパ ~「ヨーロッパ文芸フェスティバル2018」開催~

欧州発の豊かで上質な文学の魅力をより多くの日本の読者に知ってもらうために、2018年11月23日~25日の3日間にわたって、駐日EU代表部がEU加盟国大使館およびEUNIC Japan(在日EU文化機関)と共催した「第2回ヨーロッパ文芸フェスティバル2018」が、都内数カ所で開かれた。好評を博した昨年に引き続き、2度目の開催となる今回は、欧州の16カ国から16人の作家が参加。これは同時期に開かれた、文化庁および一般社団法人リットストック主催による「国際文芸フェスティバルTOKYO」と連携したイベントでもあり、欧州各国を代表する作家と彼らの優れた文学作品を、日本の人々へ紹介するための絶好の機会となった。
欧州の作家と作品にスポットを当てたユニークな文学の祭典 -Day 1-
1日目の11月23日、駐日欧州連合(EU)代表部の講堂で5つのテーマ別に行われたセッションでは、欧州各国を代表する作家はもとより、各言語のエキスパートである日本の翻訳家や研究者、司会を務めた芥川・直木賞作家など、豪華な顔ぶれが次々と登壇。作品に寄せる思いやこだわり、創作にまつわるエピソードなどを自由に熱く語り合い、作家自身による母国語での朗読も披露した。
なお、本フェスティバルの全日程のプログラム概要は、こちらの公式ウェブサイトで見ることができる。

来日した欧州人作家と、欧州文学の日本人翻訳者・研究者が繰り広げるトークや朗読に、熱心に耳を傾ける来場者。1日目には全セッションで約380人が来場した
写真提供 駐日EU代表部
第1セッション:日本語で読むヨーロッパ文学―翻訳家の仕事
ハンガリー文学が専門の早稲田みか氏は、欧州の言語から日本語へ翻訳する難しさは、「lost in translation(翻訳で失われる)」というフレーズに象徴されると指摘し、言葉を置き換える時の苦労や工夫について発表した。一方、ポーランド文学翻訳家の関口時正氏は、「翻訳で得られるもの」というポジティブな切り口で、ひらがな・カタカナ・漢字の3つの表記を使い分けられる日本語の優位性を説いた。関口氏はポーランドの古典『人形』の翻訳書(ボレスワフ・プルス作、2017年、未知谷刊)により、読売文学賞の研究・翻訳賞および日本翻訳大賞を受賞。同作の中で外国人のせりふにカタカナを用いた翻訳の具体例を挙げ、日本語表現にはまだまだ新しい可能性があると紹介した。さらにラトビア文学の翻訳家、黒沢歩氏とチェコ文学研究家の阿部賢一氏も登壇し、翻訳する上で注釈を入れるか否かなど、試行錯誤した自身の経験を語った。最後に、司会の沼野充義氏は「4人の翻訳家に共通しているのは、細部にまで気を配られた日本語の翻訳が、非常に良心的で丁寧だということ」とまとめた。
第2セッション:文学とジェンダーについて考える
自身の長編第1作『ネムレ!』の翻訳出版に合わせて来日したベルギーのアンネリース・ヴェルベーケ氏は、「女性差別と人種差別には共通するものがあり、苦しく思います」とセネガル人の夫を持つ自身の体験から語り、執筆にあたっては「人間性について書くこと、そして多様性を使うことが重要」と話した。ソ連占領下にあったラトビアの母娘の関係を描いた自作『Soviet Milk(英題)』の一部を朗読したノラ・イクステナ氏は、「世界は複雑であり、男女で人間を分断すべきではありません」と主張。女性を主人公にフィンランドの新しい犯罪小説のあり方を模索してきたレーナ・レヘトライネン氏は、「“犠牲者は女性”という既成概念を覆し、男性も女性も同じようにもろいセクシュアリティーだと示したかったのです」と語った。

女性作家という立場から、文学におけるジェンダーのあり方や自身の創作姿勢について語る、[右より]レヘトライネン、イクステナ、ヴェルベーケ、中島(司会)の各氏
写真提供 駐日EU代表部
第3セッション:日本に住む、日本を書く
谷川俊太郎などからインスピレーションを得て、自作の詩に日本語の地名を取り入れる試みをした京都在住のラウリ・キツニック氏(エストニア)、日本語に触発されて言葉遊びの感覚で創作し、ギターの伴奏で詩を朗読したアン・コッテン氏(オーストリア)、そして広告業界で執筆するかたわら、日本をモチーフにして創作活動を行う東京在住のリカルド・アドルフォ氏(ポルトガル)――日本在住の経験が自身の創作につながっているという3人の作家が、斬新でユニークな詩文の朗読を繰り広げた。

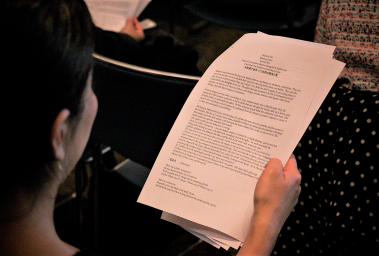
写真上:ギターの演奏と言葉とを巧みに呼応させながら詩を朗読したコッテン氏 / 写真下:フェスティバルの当日は、本邦初公開の原文や日本語訳の資料が来場者に配付された
写真提供 駐日EU代表部
第4セッション:越境する表現、その差分から見る文芸
異なるジャンルのアーティストと積極的に共同作業する作家を紹介。アイルランドのケヴィン・バリー氏は、テレビドラマの黄金期に影響を受けたと語り、テレビや舞台、映画の脚本も担当する。スペインのアンドレス・バルバ氏は写真家としても活動し、画家や版画家とのアートブック制作に関わるほか、現在進められている自身の作品の映画化にも協力している。小説のほかにアニメーション映画『アロイス・ネーベル』の原作グラフィックノベルも手掛けたチェコのヤロスラフ・ルディシュ氏は、音楽とコラボレーションした文学プロジェクト「カフカ・バンド(Kafka Band)」にも参画している。
第5セッション:EU文学賞受賞作家を紹介 -国境を越えて響き合うテーマを追求する欧州の作家たち-

近年の受賞作を集めた「EU文学賞」の記念本
写真提供 駐日EU代表部
EU文学賞(European Union Prize for Literature)は2008年の創設以来、数々の才能を発掘するために気鋭の欧州人作家に毎年贈られる賞で、現在はEU加盟国と近隣諸国を含む欧州の37カ国を幅広く対象としている。5つ目のセッション「EU文学賞受賞作家を紹介」では、ちょうど今年で10周年を迎える同賞の過去の受賞者から4人の作家を招き、芥川賞作家、小野正嗣氏の司会でディスカッションが行われた。
英国のアダム・フォウルズ氏は、19世紀に実在した詩人ジョン・クレアを主人公にした『The Quickening Maze』(『繁れる迷宮』※ )で、2011年に受賞。産業革命の渦中にある英国から次第に失われていく自然をこよなく愛し、農民詩人と呼ばれたジョンが、やがて精神に異常を来していく姿が描かれる自作について解説した。
フォウルズ氏の過去を舞台にした作品とは対照的に、2016年に『In/Half(英題)』(『イン/ハーフ』※ )で受賞したスロヴェニアのヤスミン・B・フレリヒ氏は、未来のスロヴェニア、ニューヨーク、東京を想定し、通信網が破壊され、やがてグローバル化も崩壊してしまう世界を描き出した。
小野氏は、フォウルズとフレリヒの両氏の作品について「片や歴史を、片や未来を舞台にした作品ですが、2人に共通しているのは“将来どうなるか分からない不透明な時代”を浮き彫りにしつつ、技術革新という現代性のある喫緊の問題を提起し、照射していることでは」と論じた。

写真左:『繁れる迷宮』はフォウルズ氏の長編2作目。同作は、2009年に英国の権威あるマン・ブッカー賞の最終候補にもなった。2019年1月には新作『Dream Sequence』が刊行予定 / 写真右:『イン/ハーフ』はフレリヒ氏の処女作にしてメディアの注目と批評家からの称賛を集め、スロヴェニア・ブックフェアで最優秀文学デビュー賞を受賞
写真提供 駐日EU代表部
続いて2013年の受賞者、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国出身のリディヤ・ディムコフスカ氏は、受賞作『A Spare Life(英題)』(『スペア・ライフ』※ )――頭と頭がつながった癒合双生児として生まれ、分離手術の後に生き残った一人の女性がラジオ局で語る物語――について、次のように振り返った。「これはマケドニアとユーゴスラビア(当時)が、お互いに何が何でも分離し、独立したかったという歴史の比喩なのです。2つの国で起きた歴史的な性(さが)を描いていると同時に、欧州の歴史でもあります」。
ヨルダンに生まれ、1948年にパレスチナ人離散をもたらした戦争を経験し、マルタ在住30年になるワリド・ナブハン氏は、2017年に『Exodus of Storks(英題)』(『コウノトリのエクソダス』※ )で受賞した。自身の生い立ちを基に、「国を失い、流浪の民となった大昔のユダ ヤ人の歴史が、現代のパレスチナ人にも起こっている」という視点から、ごく一般的なパレスチナ人家庭を描いた本作。主人公の母が、実はユダヤ人であるという衝撃的な事実が最後に明かされるのだが、これはナブハン氏本人もまたユダヤ人の血筋を半分引いていることに由来する。彼はマルタとパレスチナを行き来する中で、「ユダヤ人もパレスチナ人も同じ人間。お互いを敵のように思っていても、相手がいなければ自分も存在し得ない関係にあると思うようになりました」と語った。
ディムコフスカとナブハン両氏の話を受けて、小野氏は「個の歴史が、それぞれの生きている社会や国家の大きな歴史にいかに翻弄されているかという問題を扱っていて、文学に携わる両者が違う場所にいながら、お互いに響き合っていると思いました」と評した。

写真左:ディムコフスカ氏は小説のほか、詩や随筆、翻訳でも活躍し、国際的な文学賞の受賞歴多数。出版した詩集6冊と小説3冊は、20カ国語以上に翻訳されている / 写真右:ヨルダンでの避難民生活を経て、マルタと英国で勉学を修め、詩作や執筆、翻訳を手掛けるようになったナブハン氏。2014年に『コウノトリのエクソダス』で国民文学賞を受賞
写真提供 駐日EU代表部
EU文学賞を受賞したことでもたらされた変化や影響について、フレリヒ氏は、「スロヴェニアは人口200万の若い国で、誰かが後押ししてくれないと興味を持ってくれません。文学賞をいただくことで早く他の言語に翻訳されるので、どんな作家にとっても受賞は夢ではないでしょうか」と語った。ディムコフスカ氏は、「マケドニアはまだEUの一部ではありませんが、私自身は加盟を望んでいます。EU文学賞は国家レベルで認められるわけですから、マケドニアの文学にとっても大切。このような機会をいただき本当にありがたいこと」と謝辞を述べた。
「英国のEU脱退は残念ですが、自分は欧州人だというアイデンティティーを持っていますし、欧州の文学的な交流はEUが生まれるはるか以前、つまりセルバンテスとシェイクスピアの時代からすでに続いていました。また欧州人は、ジプシーと呼ばれて追いやられたロマ族の人々との関係もありました。今の排他的な空気の中で、そういった歴史を思い出すことは大事です」と語ったのはフォウルズ氏。
ナブハン氏は、「マルタに住んで30年たち、やっと『私の国』だと言えるようになりました。信じてください、受賞時にはマルタ国民から英雄のような扱いを受けたのです。いい作品は旅する翼を持っているのです」と結んだ。
第6セッション:オープニングセレモニー -文学を通して欧州と日本のつながりを醸成する-
1日目の最後のセッションとして、パトリシア・フロア駐日EU大使が各セッションの参加者から1人ずつ壇上へ招き、共に初日を締めくくった。

「本フェスティバルの目的の一つは、国と国の間でつながりを醸成すること。また、私たちが何をもって『人である』のか、『何が文学なのか』を考える機会にもなった」と語るフロアEU大使
写真提供 駐日EU代表部
翻訳家と一緒に仕事をする上で、バリー氏は「アイルランドのユーモアは、いわゆるブラックユーモアが多いので、『コメディーだったのですか?』と後で驚かれることもあります。隔たりを埋めるためには、何よりも翻訳家と知り合いになること。執筆の際には、言葉のリズム感や音楽的な要素を大事にしています」と答え、これに対してイクステナ氏も「多様な言語があってよかったと思います。これだけ翻訳をしてくれるというのは、それだけ新たな生命が吹き込まれることですから」と共鳴した。
「自分の頭の中で、マルタ語、アラビア語、英語の3カ国語が並んで翻訳されるのも、何ら不思議ではありません。しかし言語だけでなく文化も理解していないと、翻訳はできないでしょう。私は30年かけて、ようやくマルタの言葉で自身を表現できるようになりました」(ナブハン氏)
「20世紀前半に活躍した英国の東洋学者、アーサー・ウェイリーの訳したアジアの詩から、私は大きな影響を受けました。ウェイリーによる日本語、中国語からの英訳への美しさは、もしかしたら単なる翻訳というよりも、モダニズムの基盤として英語にもっと多くの恩恵をもたらしたのではないでしょうか。これも欧州とアジアの間で生まれた交流だったと思います」と、コッテン氏は先人の偉業を称えた。
フロア大使は「こういった皆さんのお話から、欧州とアジアの世界文学のつながりを見ることができましたが、本フェスティバルは、国と国の間でつながりを醸成することも目的の一つ。私たちが何をもって『人である』のか、『何が文学なのか』を考えることができたと信じています」と統括。この後、登壇者や関係者、一般来場者と共に、和やかな雰囲気の中で祝杯を上げた。
当日はこのほか、サブ会場である同代表部内のクーデンホフ=カレルギーの間で、「『オランダ小史』邦訳刊行記念対談」や、ギター伴奏付きの「アン・コッテン朗読会『ロッジアと餓鬼ども』」も併行した。
駐日EU代表部の公式ツイッターで本フェスティバルを知り、同じ都内の会社で誘い合って来たという女性2人は、「自分でも文芸翻訳を勉強しているので、とても刺激になりました」「さまざまな背景を持った作品を作家自身の声で、多言語の響きで聴くことのできる、非常に貴重な機会でした」とにこやかに感想を語った。

ロビーではセッションの合間に書籍の販売も行われ、来場者でにぎわった
写真提供 駐日EU代表部
その他のトーク・朗読・上映イベント -Day 2-
開催2日目、11月24日のメイン会場となったイタリア文化会館(千代田区)では、第1セッションで「日本におけるヨーロッパ文学の出版事情」と題し、翻訳書の出版事情に通じたエージェントや編集者がパネルディスカッションを行った。過去のヒット作の舞台裏など一般の読者にとって興味深い話から、各社の初版部数や翻訳出版企画の持ち込み事例など、業界の関係者でもなかなか聞けない貴重な話まで、さまざまな話題で盛り上がった。第2セッションでは、ドイツで話題の作家トーマス・メレ氏が『背後の世界』(2018年10月、河出書房新社刊)を朗読し、同作を翻訳した金志成氏、作家の町田康氏と共にトークを展開。また最後に、イタリア文学の最高峰「ストレーガ賞」を受賞したパオロ・コニェッティ氏が、邦訳が刊行されて間もない『帰れない山』(関口英子訳、2018年10月、新潮クレスト・ブックス)を朗読し、小説家・編集者の松家仁之氏と対談した。

前月に日本語訳が出版されたばかりの『背後の世界』を巡ってトークを繰り広げるメレ、金、町田の各氏(左より)
© Goethe-Institut, Foto Yota Kataoka
そのほか、アンスティチュ・フランセ東京(新宿区)では、「文学とコミットメント:21世紀に女性であること」と題して、『ヌヌ 完璧なベビーシッター』(松本百合子訳、2018年3月、集英社刊)の作者レイラ・スリマニ氏が日本の直木賞作家、桐野夏生氏と対談。またチェコセンター東京(渋谷区)では、前日のメインイベントでも登壇したヤロスラフ・ルディシュ氏原作のグラフィックノベルをアニメーション化した『アロイス・ネーベル』が上映され、ルディシュ氏とチェコ文学研究家の阿部賢一氏との対談が行われた。
これらのイベントと併行して、HMV&BOOKS SHIBUYAでは、1部でヴェルベーケ氏(ベルギー)が『ネムレ!』出版記念トークを行ったほか、2部でケヴィン・バリー氏(アイルランド)が自作を朗読し、スペシャルゲストとして翻訳家の柴田元幸氏も登壇した。

HMV&BOOKS SHIBUYAではトークの後にサイン会も行われた。ファンの要望に笑顔で応えるヴェルベーケ氏
© Rob Walbers
「海外マンガフェスタ2018」にEUもブースを出展 -Day 3-
最終日となる11月25日は、東京ビッグサイト(江東区)で開催された自主制作漫画誌展示即売会「コミティア」の中の、「海外マンガフェスタ」にEUもブースを出展。常連のフランスやスペインに加えて、今年はポーランドも参加した。またチェコ、ブルガリア、ドイツ、オーストリア、イタリア、アイルランドなどで人気のある作品も展示された。

欧州発の漫画作品を紹介するEUのブース。漫画家自身によるライブドローイングなども披露され、来場者は興味津々に見入った
写真提供 駐日EU代表部
同日、本フェスティバルの締めくくりとして、ベルギー王国大使館で同国フランダース政府文化大臣同席の下、閉幕イベントが行われ、フェスティバルに参加した作家たちが、欧州文学に関心を寄せる日本の作家、研究者、編集者たちと交流を楽しんだ。
※ これら4作品については、本フェスティバルのために日本語の抄訳が作られた。作品そのものは国内未刊行
人気記事ランキング
新着記事
-
 EUの付加価値税
EUの付加価値税2024.11.15
WHAT IS THE EU?
-
 癒しのフィンランド装飾―「ヒンメリ」作家・山本睦子さんを訪ねて
癒しのフィンランド装飾―「ヒンメリ」作家・山本睦子さんを訪ねて2024.11.7
EU-JAPAN
-
 「隣は何をする人ぞ」―ポーランド詩人招き、朗読&パフォーマンス
「隣は何をする人ぞ」―ポーランド詩人招き、朗読&パフォーマンス2024.11.6
EU-JAPAN
-
 国連「未来サミット」へのEUの関与や成果について教えてください
国連「未来サミット」へのEUの関与や成果について教えてください2024.10.28
Q & A
-
 EUにおける男女間賃金格差の是正
EUにおける男女間賃金格差の是正2024.10.21
FEATURE
おすすめ記事
-
 EUにおける男女間賃金格差の是正
EUにおける男女間賃金格差の是正2024.10.21
FEATURE
-
 国連「未来サミット」へのEUの関与や成果について教えてください
国連「未来サミット」へのEUの関与や成果について教えてください2024.10.28
Q & A
-
 「隣は何をする人ぞ」―ポーランド詩人招き、朗読&パフォーマンス
「隣は何をする人ぞ」―ポーランド詩人招き、朗読&パフォーマンス2024.11.6
EU-JAPAN
-
 癒しのフィンランド装飾―「ヒンメリ」作家・山本睦子さんを訪ねて
癒しのフィンランド装飾―「ヒンメリ」作家・山本睦子さんを訪ねて2024.11.7
EU-JAPAN

