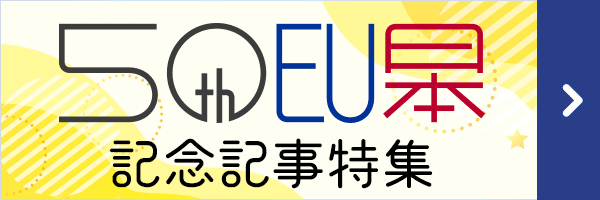2024.6.3
EU-JAPAN
日・EU共同研究を通じた次世代輸送燃料の追求

気候危機に対処し、パリ協定の野心的な目標を達成するためには、化石燃料から環境により優しい燃料へと速やかに移行する必要がある。欧州連合(EU)と日本の「高度バイオ燃料と代替再生燃料」共同研究プロジェクトにおける双方の研究者、研究機関および産業界の協力は、画期的なイノベーションの好例であり、「これらの分野での欧州と日本の技術基盤の強化にもつながる」(マリヤ・ガブリエル前欧州委員会イノベーション・研究・文化・教育・青少年担当委員)。ここでは、同プロジェクトについて具体的に説明する。
科学技術における二者間協力
科学技術分野におけるEUと日本の協力は、2009年に署名、2011年に発効した「日・EU科学技術協力協定」に基づいている。同協定によって設置された政府間討議の枠組み「日・EU科学技術協力合同委員会」は、2023年12月までに7回行われている。2024年4月には、イリアナ・イヴァノヴァ欧州委員会イノベーション・研究・文化・教育および青少年担当委員の訪日に合わせ、駐日EU代表部で、同協定署名15周年を記念したレセプションも開催された。

また、EUと日本は2015年5月、 研究・イノベーションにおける一層緊密な関係に向けた 「共同ビジョン」および日本国政府と欧州委員会との間の研究・イノベーションにおける新たな戦略的パートナーシップという二つの重要な文書を採択。2018年には日・EU戦略的パートナーシップ協定、2020年には科学技術・イノベーション協力の強化に関する合意文書を締結し、両者は科学技術分野における対話と協力を深化させてきた。
EUの研究・イノベーション支援枠組み計画「ホライズン・ヨーロッパ」(2021~2027年)には、日本からも応募することができる。ただ、日本は第三国かつ助成対象外であるため、予算を独自に確保するか、例外的助成を申請する必要がある。
合成燃料を共同研究開発
そうした流れの中、EUと日本は2021年4月、日・EU科学技術協力協定に基づき、「高度バイオ燃料と代替再生燃料」に関する以下3件の共同研究プロジェクトを開始することを発表。「ホライズン2020」(現「ホライズン・ヨーロッパ」)から950万ユーロ、日本の国立研究開発法人・科学技術振興機構(JST)が管轄する「戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)」から約120万ユーロの計1,070万ユーロの助成が提供されている。
| LAURELIN | 大型車の燃料として活用が期待される再生可能メタノールに特化したプロジェクトで、磁気誘導、非熱プラズマ誘導、マイクロ波などの技術を活用し、二酸化炭素の水素化に関する画期的な触媒システムと新技術の開発を目指す。 |
| 4AirCRAFT | 市場が拡大している航空輸送で急務となっている低排出・実質排出ゼロの燃料に関するプロジェクトで、3つの触媒を組み合わせた新しい多段階リアクター技術を開発し、航空用に直接二酸化炭素を液化燃料化する効率的な燃料合成を目指す。 |
| ORACLE | 船舶の燃料として活用が期待される再生可能アンモニアを、窒素と水から合成することを目的とするプロジェクトで、電気化学触媒、プラズマ触媒、熱触媒の3反応経路によるアンモニア合成法を開発・検証し、アンモニアを現地生産することを目指す。 |
これらのプロジェクトはいずれも、欧州委員会の研究・イノベーション総局とJSTとの緊密な協力関係から生まれたもので、新型燃料の開発とイノベーションに新たな知見をもたらし、EUと日本のクリーンテクノロジーと気候変動対策に貢献することが期待されている。持続可能な合成燃料(e-fuel)※は、温室効果ガス排出削減に効果があるため、その重要性が増している。
※ e-fuel:再生可能エネルギー由来の水素と二酸化炭素を合成して製造される燃料
これらプロジェクトの大半はほぼ中間点に達し、触媒などのプロセスや新規化学反応器などのプロセス機器に加え、新規燃料反応器の製造と展開の課題に関しても、非常に興味深い科学結果が得られている。これらの共同研究を受け、日本が「ホライズン・ヨーロッパ」に準加盟する可能性についての議論も活発化している。
各プロジェクトの概要
いずれのプロジェクトも、低コストのバイオエネルギーキャリア、非食糧・飼料ベースの高度バイオ燃料、水素を超える代替再生可能燃料を調達するための、劇的変化を及ぼす高性能な新規触媒技術の開発に特化している。EUと日本の独立した専門家からなる審査委員会は、30件の提案を評価し、最終的に有効な提案26件の中からこの3件を採択した。
1. LAURELIN

LAURELIN プロジェクトは、再生可能燃料であるメタノールを製造するための二酸化炭素の水素化プロセス(通常は触媒を用いた、水素分子と他の化合物や元素との化学反応)の最適化と改良に焦点を当てている。その主な目的は、二酸化炭素変換によるメタノール生産において、より優れた選択性(触媒が特定の物質だけと反応して、ある目的の物質だけを生成する性質)、収率(理論上得られる最大量に対する実際に得られた量の比率)およびエネルギー効率を達成することである。これら新技術によって得られた「グリーンメタノール」の活用は、輸送部門の二酸化炭素排出量削減に大きく貢献し、気候変動緩和に寄与することが期待される。マイクロ波、電磁誘導、非熱プラズマといった高度な反応プロセスに完璧に適合する新世代の触媒を導入することで、さまざまな限界に立ち向かうことだ。なお、従来の熱触媒反応は、上記3つの触媒に対するベンチマークとして利用する。
- プロジェクト期間:4年
- パートナー数:10(EU、日本、英国)
- プロジェクト・コーディネーター: AIMPLASプラスチック技術センター(スペイン)
2. 4AirCRAFT

航空分野は、運輸部門の中で自動車分野次いでエネルギー需要が高く、エネルギー密度の高い燃料に大きく依存している。ここ数十年の大いなる技術的進歩を通じて、航空会社、航空機メーカーおよび政府はエネルギー効率の向上を目指してきたが、化石燃料に代わる燃料を見つけるのに腐心している。EU域内では、運輸部門の温室効果ガス排出量の13%を航空分野が占めているのが現状だ。
残念なことに、現行の航空燃料製造技術は化石資源の使用に大きく依存しており、エネルギー効率の欠如に加えて、低い選択性と変換効率に悩まされることが多い。そのため、新技術による解決策が求められており、反応経路の主要段階におけるエネルギー障壁を低減する触媒材料の合理的な設計が不可欠である。
4AirCRAFTプロジェクトは、従来の反応経路に比べてはるかに穏やかで環境に優しい条件の下で、二酸化炭素をジェット燃料域の炭化水素に直接変換するという、革新的な技術の開発を目指している。その実現に向けて、触媒材料の合理的な設計と触媒環境の調整を共同開発し、検証・活用を進めている。4AirCRAFTの技術は、二酸化炭素を循環的に利用することでその排出量全体を削減し、循環経済と化石燃料の代替に貢献できる。ひいては、世界的なエネルギー問題の解決、EUのエネルギー安全保障の強化および持続可能な運輸部門の構築にもつながる。
- プロジェクト期間:3~4年
- パートナーの数:9(EU、日本、ブラジル)
- プロジェクト・コーディネーター:アラゴン新水素技術開発財団 (スペイン)
3. ORACLE

ORACLEプロジェクトは、アンモニア合成のための革新的な技術の確立に焦点を当てている。これまでの大規模な一極集中型アンモニアプラントではなく、ORACLEのパートナーは、風力タービンや太陽電池といった再生可能エネルギーと併設可能な、小規模な分散型アンモニア合成設備技術を開発している。
ORACLEでは、代替再生燃料としての分散型アンモニア合成を目的とした触媒の研究とコンセプトの開発を進めており、電気化学触媒反応、プラズマ触媒反応および熱触媒反応の3種類の経路におけるアンモニア合成法を開発・検証。これまでの実証試験とパートナー間の長年の協力関係をベースに、触媒と反応器を開発することによってアンモニアを製造する3つの方法を調査している。
- プロジェクト期間:4年
- パートナーの数:8(EU、日本)
- プロジェクト・コーディネーター:オーフス大学(デンマーク)
化石燃料からの転換を目指して
2023年11月には、東京で、3つのプロジェクトの研究者が一堂に会し、知見や研究成果を交換するためのイベントを実施。ジャン=エリック・パケ駐日EU大使や森本茂雄JST理事も出席した。同様のイベントが2024年後半に欧州で行われる予定だ。
日・EUの研究者が共同でプロジェクトを推進することで得られる効果の一例として、大規模な多国間研究プロジェクトに参加し、設計・実施などさまざまな段階を経験することで多くの知識を獲得できることが挙げられる。また、産業界との協力関係の拡大、科学コミュニケーションスキルの向上なども大きな効果だ。上記のいずれのプロジェクトにおいても、コミュニケーションはすべて英語で行われている。

化石燃料からの転換を図るためには、さらに多くの研究が必要であり、科学と産業のそれぞれの領域において明確な目標を設定した上で、共に発展するためには、安定的かつ予測可能な規制の枠組みを構築することが求められる。
化石燃料は段階的に廃止されるべきだが、それ以外の特定の種類の燃料の使用については、いかなる決定も下すべきではないという点で、日・EU双方の研究者の意見は一致している。電源構成はさまざまな要因の影響を受けるものであり、中でも再生可能エネルギーの選択は、国や地域がそれぞれの事情を考慮して決定すべきだ。実際にエネルギーの生産方法については、太陽光、風、水など、各国・地域の資源の使いやすさに大きく関わっている。
【関連記事】よりよい未来へ!ホライズン・ヨーロッパ始動(2021年8月)
人気記事ランキング
新着記事
-
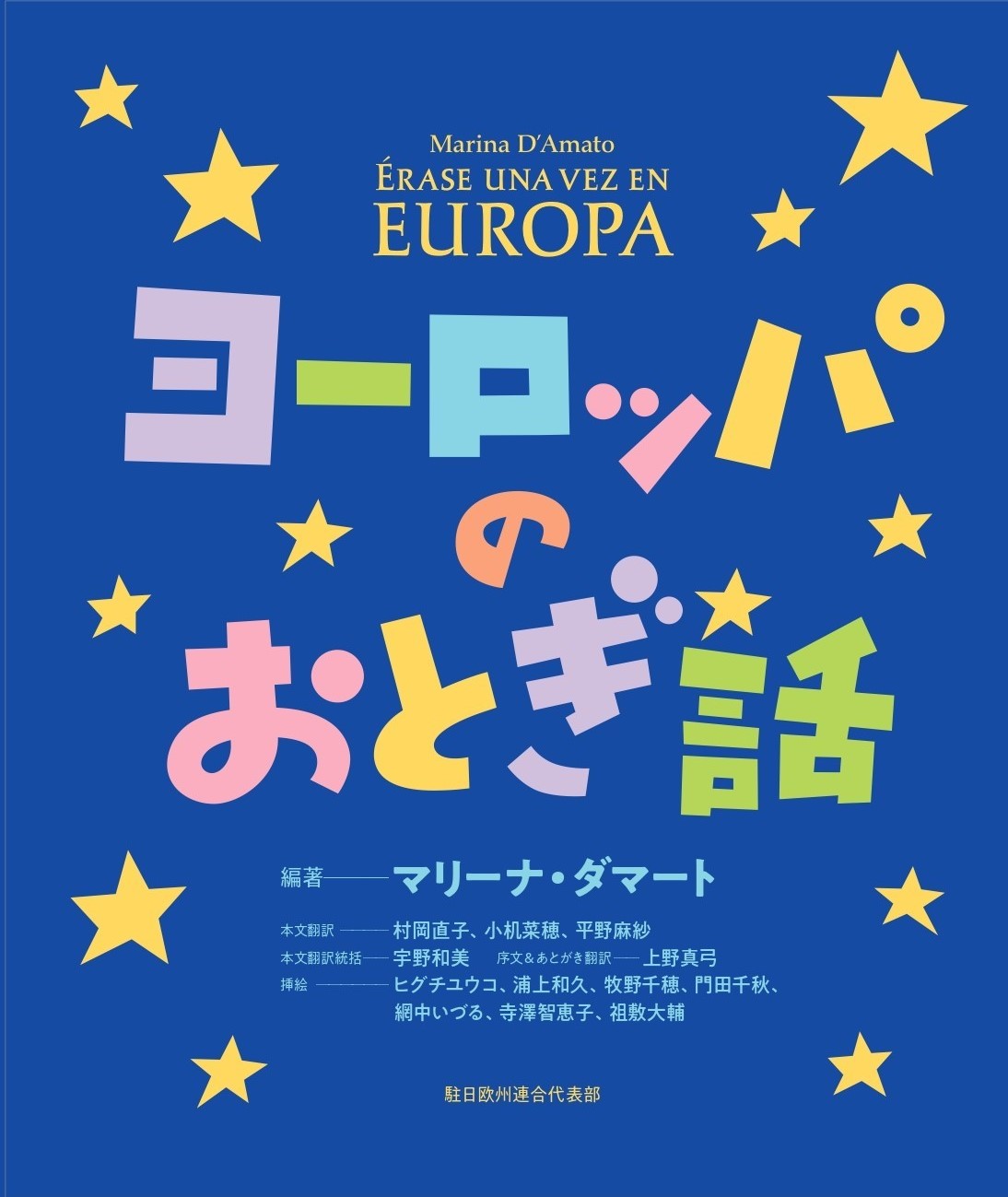 おとぎ話で出会うヨーロッパ―EUの絵本、大阪・関西万博に登場
おとぎ話で出会うヨーロッパ―EUの絵本、大阪・関西万博に登場2025.4.14
FEATURE
-
 女性が輝く社会へ、日・EUで政治、職場の未来を協議―国際女性デー記念セミナー
女性が輝く社会へ、日・EUで政治、職場の未来を協議―国際女性デー記念セミナー2025.4.11
EU-JAPAN
-
 チェコから巨人へ―日本プロ野球界初のEU出身選手・フルプの挑戦
チェコから巨人へ―日本プロ野球界初のEU出身選手・フルプの挑戦2025.3.26
EU-JAPAN
-
 小さな国から大きな発信—駐日リトアニア大使のパブリック・ディプロマシー戦略
小さな国から大きな発信—駐日リトアニア大使のパブリック・ディプロマシー戦略2025.3.18
EU-JAPAN
-
 障がいのある学生がEU大使と交流―「Go!Go!Embassy!」イベント開催
障がいのある学生がEU大使と交流―「Go!Go!Embassy!」イベント開催2025.2.27
EU-JAPAN
おすすめ記事
-
 障がいのある学生がEU大使と交流―「Go!Go!Embassy!」イベント開催
障がいのある学生がEU大使と交流―「Go!Go!Embassy!」イベント開催2025.2.27
EU-JAPAN
-
 小さな国から大きな発信—駐日リトアニア大使のパブリック・ディプロマシー戦略
小さな国から大きな発信—駐日リトアニア大使のパブリック・ディプロマシー戦略2025.3.18
EU-JAPAN
-
 女性が輝く社会へ、日・EUで政治、職場の未来を協議―国際女性デー記念セミナー
女性が輝く社会へ、日・EUで政治、職場の未来を協議―国際女性デー記念セミナー2025.4.11
EU-JAPAN
-
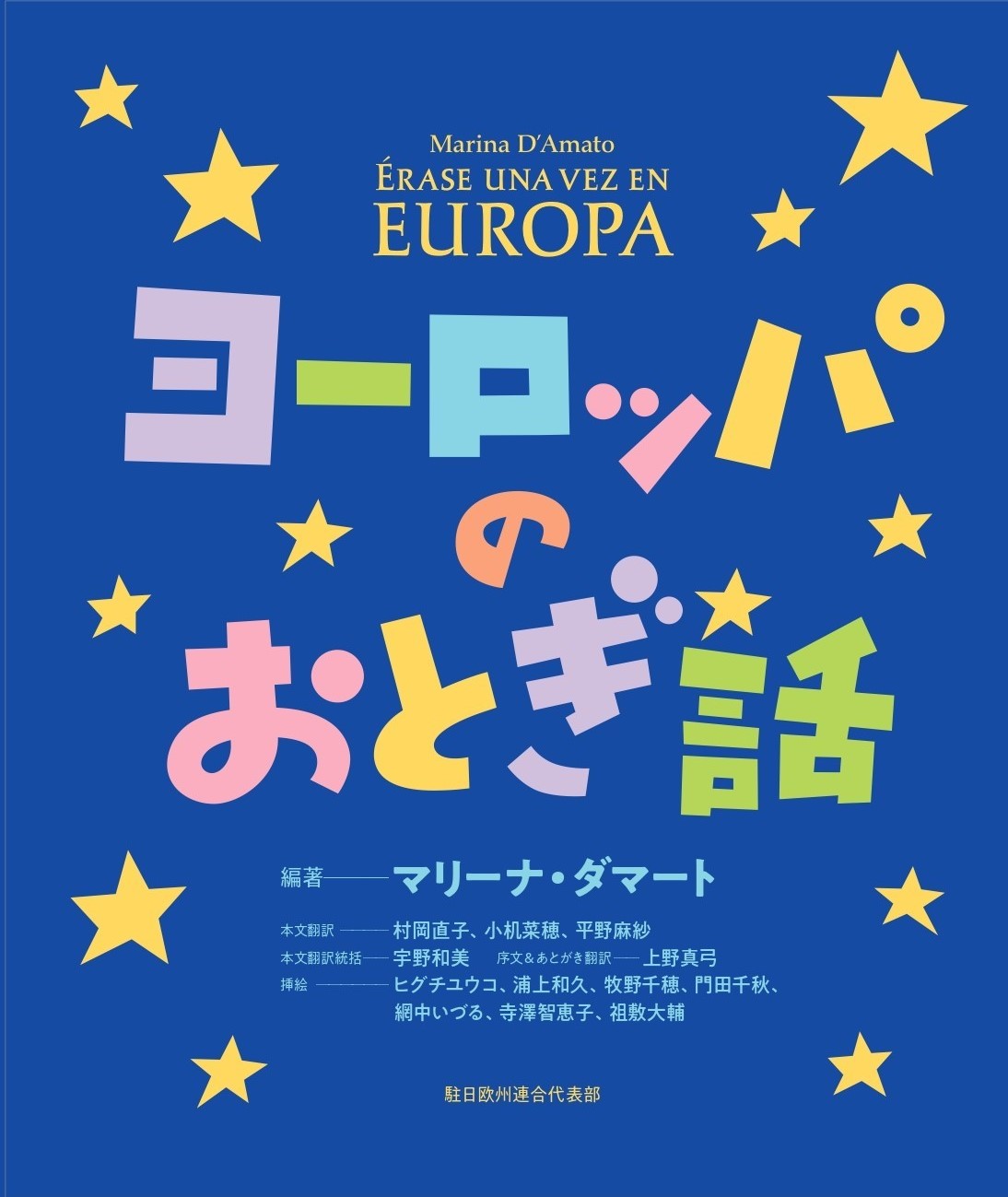 おとぎ話で出会うヨーロッパ―EUの絵本、大阪・関西万博に登場
おとぎ話で出会うヨーロッパ―EUの絵本、大阪・関西万博に登場2025.4.14
FEATURE